- TOP
- >
- 秋の夜長はしっぽり日本酒で愉しむのがツウ!ー『ビジネスエリートが知っている 教養としての日本酒』より
新着ニュース30件
2021年10月28日 23:00
そこで、『ビジネスエリートが知っている 教養としての日本酒』(あさ出版)の著者である友田晶子さんに、秋ならではの日本酒の愉しみ方について、話してもらった。秋の夜長に、日本酒をしっとり愉しみたい。
季節ごとに日本酒を変えて楽しむ。
日本には春夏秋冬と四季があることから、食材の特徴を活かして創作される和食は、季節感あふれるものとなり、盛り付けにも季節が演出され、それが和食の魅力となっている。同じように、日本酒にも、四季ごとの楽しみ方があるのだ。四季を感じられるお酒というのは世界を見渡しても日本酒だけではないだろうか。もちろん、ワインにもボジョレー・ヌーヴォーやホイリゲに代表されるような新酒があるし、焼酎にも秋に収穫したばかりのサツマイモを使って造る新焼酎もある。
しかし、春には春の、夏には夏の、秋には秋の、そして冬には冬の、それぞれの季節ならではのお酒ができ、市場に出回り、それを手にする人が「ああ、もうこの季節がきたか」と強く実感できるのは日本酒だけだ。
会食や接待といった場面では、料理や部屋の設えのみならず、いただく酒にも季節感を取り入れたセレクトをすることで、場も盛り上がり話題が広がり、相手にもよろこばれるとともに、教養ある人と一目置かれることだろう。
秋の酒の愉しみ方は、バリエーション豊か
収穫の秋。新米が蔵に運ばれ、蔵では酒造りが始まる。酒造メーカーは、秋から冬にかけてもっとも忙しい季節だ。酒造りには、おおむね3カ月。10 月に造り始めれば、早ければ年内に、いわゆる「新酒」ができあがるため、新たな年を「新酒」で祝うこともできる。「新酒」とは、秋から3月頃までに造られた酒のことを指し、できたてのお酒を搾ったものを「搾り立て」というが、その年最初に仕込まれたお酒の搾り立てをとくに「初搾り」と言われる。
さらにこの季節だけ味わえるのが「あらばしり」。搾った最初にほとばしり出てくる部分のみを瓶詰めしたもので、いわば、一番搾り。昔は蔵でしか飲めなかった希少価値の高い酒だ。
秋にはもう一つ、楽しみがある。前の冬に造った「新酒」を一度火入れし、涼しい蔵内でひと夏寝かせ、そのまま火入れをしないで瓶詰めして出荷する「ひやおろし」が市場に出回る季節。涼しい蔵の中で保存された冷たい酒を市場に卸すから「ひやおろし」という。
ひと夏寝かした酒は、なめらかになり、うま味がのり、コクが出る。「ひや」という言葉がついているので冷酒のことかと思うかしれないが、そうではなく、むしろ、お燗にするとおいしい酒だ。秋になると味わいがぐっと増すので「秋あがり」とも呼ばれることもある。
風味豊かなキノコや滋味たっぷりのジビエ、脂ののった秋刀魚や鮭など、秋の食材とは最高の相性。また、ふた夏寝かせた「2年熟成 ひやおろし」など、より熟成感を増したタイプも登場している。よりまろみが加わった、味わい深いところが魅力だ。
今年の秋に楽しみたいお酒 はコチラから → あさ出版note https://note.com/asapublishing/n/ne0c78818ac9e
【書籍概要】
書籍名:ビジネスエリートが知っている 教養としての日本酒
著者:友田 晶子
288ページ
2020年10月22日発売
価格:1,760円(税込)
-->
記事検索
ユニーク特集

株式会社ファーストキャビン

変態企業カメレオン

株式会社エイタロウソフト

株式会社GABA

株式会社リクルートエージェント
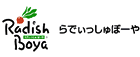
らでぃっしゅぼーや株式会社

株式会社ツナグ・ソリューションズ

株式会社ネビュラプロジェクト

使えるねっと株式会社

株式会社ECC
アクセスランキング トップ10
お問い合わせ
モバイルサイトQRコード
Chu-Kansモバイルサイトへアクセス
htt





